最近産経ニュースで「夏でもマスクを外さない若年層」をテーマに据えた記事を目にした。
内容を要約すると
「コロナ禍をきっかけに、マスクが“衛生用具”であるとともに“心の防具”の側面も持つようになった。特に若年層では自己肯定感や社会不安との深い関係が明らかになってきている。社会としてはマスクをつける自由も外す自由も認める寛容さと多様性への理解が求められていると言える。」
といったところだ。
外す者も外さない者にも理解を示しつつ、専門家の意見を交えながら最終的にふわっと解決策を模索する形で締めくくっている。
記事の良い悪いはよく分からないが、筆者は違和感を覚えた点があった。
この記事だと、あたかもマスクを外せない若者がコロナ禍以降急に現れたように見える。
ん〜?どう?今更感ない?ネット文化においては10年以上も前から“演出の手段”として定着してなかった?
2009年頃の初期配信文化
2009年あたりからニコニコ生放送の認知度が上がり、2010年からはツイキャスが開始された。顔出し配信の黎明期に当たるのがこの頃。
この頃から既に、顔を隠すことで雰囲気や声に集中させたり、素顔を見せないことで“想像の余地”を作るという文化があった。
なんなら、「顔に自信がない」「鼻や口元など特定のパーツが嫌い」という理由でマスクを着用する配信者も出現していた。
そんで、2012〜2015年頃にはマスクが“キャラ補正”や“美的補正”のアイテムとして定着してたと覚えている。
この頃から「マスク詐欺」「マスク美人/マスクイケメン」という言葉が出現。
最早マスク着用は単なる「隠し」ではなく、「小顔に見える」「美人/イケメン風に見える」といった“顔のブースト効果”としても使われ始めていた。
逆にマスクを外したことでファンが離れてしまう、いわゆる
ぶっコ抜(ぶっさwコミュ抜けるわw)
が多く発生したのもこの頃だ。
そうした“隠すことで魅力が引き立つ”という感覚は、コロナ禍から急に現れたわけじゃなく、むしろそこそこ長い時間をかけてネットを中心に若者文化の中で醸成されたはず。
にもかかわらず、最近では「コロナが若者をマスク依存にした」というストーリーが一人歩きし、それを根拠に「コロナが終わったのだからマスクを外すべきだ」と声高に主張する人々もいる。
私が気に入らないのは、そうした人々が文化的背景を無視して、自身の主張の正当化に都合よく“マスク文化”を利用していることだ。
新型コロナウィルス感染症は触媒であって起源ではない
もちろん、コロナ禍はマスク着用の常態化において一つの大きな転機だったことは否定しない。
しかし、私はそれが“出発点”だったとは思っていない。
むしろ、それ以前からネットの中で育まれていた「顔を隠すことの快適さ」や「自己の外見をコントロールする文化」が、
コロナをきっかけに一気に日常空間へと押し広げられただけのことだ。
たとえば、2ちゃんねる発のネットスラング(リア充や草など)が、若者たちの日常会話に“いつの間にか”入り込んでいったように、
マスク文化もまた、時間差で現実の風景になっていくのはほぼ必然だったと感じている。
だからこそ「コロナが若者をマスク依存にした」とする論調には違和感がある。
コロナは引き金ではあっても、根本的な原因ではない。
本質的には、すでに文化として存在していたものが、単に“リアルに進出した”だけなのだ。
問題は「マスクの有無」ではない。
それを巡る物語を、誰が、どの目的で操作しているのかという視点が、今こそ必要なのだと思う。


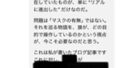
コメント